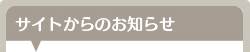リスタ・コンディショニング・ルームの施術例

憂うつな気分とマイナスな考えが抜けないで困っているうつ病の方
-
頭
-
背中
-
メンタル
-
男性
-
40代
2022.12.22
 病院での診断
病院での診断
うつ病
 これまでの経過
これまでの経過
※今回の掲載は本人に了解を得ている事例であることと、個人を特定できないように施しております。
2年前の4月に50人を使うプロジェクトのリーダーとなりプレッシャーを強く感じるようになる。
仕事を進めていくうえで、そもそもプロジェクトの進め方が自分でもよくわからないのに加えて、プロジェクトメンバーとの関係性やメンバー同士間の関係調整の問題など、次々と問題が起きている状況であった。
仕事に対するストレスから、その年の10月ごろより会社に行くのが辛くなりはじめる。
状態としては、目がさめると会社での嫌なことが頭に浮かん来るために、会社に行くのが非常に困難になっていた。
また、自分がちゃんとできていないという自責の念が増大してきて、職場にいるだけでストレスとなって集中はできないし決断もできなくなってきていた。
年が明けて1月会社の提携医療機関を受診。休養が必要と言われる。
翌週には自宅近くの精神科を受診。うつ病と診断される。
以後、休職となる。
薬物療法と休養を3か月続けたころの4月に主治医に当ルームを紹介される。(紹介理由は認知行動療法の依頼)
なお、当ルームの初診時に本人が鍼治療も希望されたために、患者さんの希望を汲んで鍼治療と認知行動療法を併用する『心療鍼灸』を行うこととした。
主治医には、患者さんの希望もあり『心療鍼灸』で行う旨の報告書をお送りして許可を得ている。
職業:会社員
性格:真面目、神経質、内向的、怖がり、本人の言葉では石橋をたたいても渡らないようなタイプ
既往歴(過去に大きな病気をした経験):5年前にうつ病(薬物療法のみ)
お酒:日にビールを350ml
タバコ:吸わない
趣味:野球とゴルフ
家族:妻・30代
結婚:3年・夫婦仲は良好
夫婦ともに子供を希望している。
2年前の4月に50人を使うプロジェクトのリーダーとなりプレッシャーを強く感じるようになる。
仕事を進めていくうえで、そもそもプロジェクトの進め方が自分でもよくわからないのに加えて、プロジェクトメンバーとの関係性やメンバー同士間の関係調整の問題など、次々と問題が起きている状況であった。
仕事に対するストレスから、その年の10月ごろより会社に行くのが辛くなりはじめる。
状態としては、目がさめると会社での嫌なことが頭に浮かん来るために、会社に行くのが非常に困難になっていた。
また、自分がちゃんとできていないという自責の念が増大してきて、職場にいるだけでストレスとなって集中はできないし決断もできなくなってきていた。
年が明けて1月会社の提携医療機関を受診。休養が必要と言われる。
翌週には自宅近くの精神科を受診。うつ病と診断される。
以後、休職となる。
薬物療法と休養を3か月続けたころの4月に主治医に当ルームを紹介される。(紹介理由は認知行動療法の依頼)
なお、当ルームの初診時に本人が鍼治療も希望されたために、患者さんの希望を汲んで鍼治療と認知行動療法を併用する『心療鍼灸』を行うこととした。
主治医には、患者さんの希望もあり『心療鍼灸』で行う旨の報告書をお送りして許可を得ている。
職業:会社員
性格:真面目、神経質、内向的、怖がり、本人の言葉では石橋をたたいても渡らないようなタイプ
既往歴(過去に大きな病気をした経験):5年前にうつ病(薬物療法のみ)
お酒:日にビールを350ml
タバコ:吸わない
趣味:野球とゴルフ
家族:妻・30代
結婚:3年・夫婦仲は良好
夫婦ともに子供を希望している。
 鍼灸院としての診断
鍼灸院としての診断
精神科でうつ病と診断されているので、QIDS -JとCMI健康調査票を用いて現在の状態の確認をした。
QIDS -J(簡易抑うつ症状尺度):15(中等度)
CMI健康調査票:領域Ⅲ(どちらかといえば神経症の可能性が強い)
なお、身体的自覚症の項目では、疲労度/習慣が高得点であるのと、精神的自覚症の項目では、不適応/抑うつ/不安が高得点であった。
※CMI健康調査票は身体的自覚症(12系統別)と精神的自覚症(6状態別)を把握と、そこから神経症(ストレスによって精神が疲弊した状態)かどうかの確認をする検査
QIDS -J(簡易抑うつ症状尺度):15(中等度)
CMI健康調査票:領域Ⅲ(どちらかといえば神経症の可能性が強い)
なお、身体的自覚症の項目では、疲労度/習慣が高得点であるのと、精神的自覚症の項目では、不適応/抑うつ/不安が高得点であった。
※CMI健康調査票は身体的自覚症(12系統別)と精神的自覚症(6状態別)を把握と、そこから神経症(ストレスによって精神が疲弊した状態)かどうかの確認をする検査
 治療方針
治療方針
患者さんの希望もありまた、行うことに問題ないために鍼治療と認知行動療法の併用で進める。
鍼治療として、
1、うつ病の場合、脳の血流量が低下しているために脳血流の改善とセロトニンの活性化。
2、特に左前頭葉の血流量の改善。(うつ病は左前頭葉の血流量が低下していることが研究などで報告されている)
3、背部や頸部の痛みに対しては、痛みを訴えたときのみ対応する。
4、ホームワーク(自宅で行ってもらうこと):ウォーキングなどの運動療法や行動活性化という方法を用いる。
今回は、抑うつ気分とネガティブな考え方が主に訴えているために、鍼治療と認知行動療法の併用とホームワーク(自宅で行ってもらうこと)で施術を進めることとした。
方法としては、施術時間は50分で最初に認知行動療法を20分~30分。その後、鍼治療を20分~30分行うことにした。
鍼治療として、
1、うつ病の場合、脳の血流量が低下しているために脳血流の改善とセロトニンの活性化。
2、特に左前頭葉の血流量の改善。(うつ病は左前頭葉の血流量が低下していることが研究などで報告されている)
3、背部や頸部の痛みに対しては、痛みを訴えたときのみ対応する。
4、ホームワーク(自宅で行ってもらうこと):ウォーキングなどの運動療法や行動活性化という方法を用いる。
今回は、抑うつ気分とネガティブな考え方が主に訴えているために、鍼治療と認知行動療法の併用とホームワーク(自宅で行ってもらうこと)で施術を進めることとした。
方法としては、施術時間は50分で最初に認知行動療法を20分~30分。その後、鍼治療を20分~30分行うことにした。
 治療内容
治療内容
1、脳血流改善を目的に、四肢末端への鍼治療プラス低周波鍼通電(20分程度)(どこのツボではなく肘から先と膝から先に鍼治療を行うことで、脳血流が改善することがわかっている)
2、脳血流改善を目的に、頭のてっぺん付近(ツボ名は百会)と眉間(ツボ名は印堂)に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分程度)
3、脳血流改善を目的に、特に左前頭葉の2か所に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分程度)
4、耳に置鍼(20分程度)(脳血流が改善することがわかっている)
5、患者さんが希望したときのみ、背部と頸部にに置鍼(20分程度)
※置鍼とは、鍼を刺入した状態で置いておくこと。
初診時
現在の困りごとを伺いうつ病のテストとしてQIDS -Jを行う。
次に、症状や状態の説明を認知モデル/認知行動モデルで説明を行った後に、認知行動療法を行いその後、上記の内容の鍼施術を行った。
ホームワークとしては、CMI健康調査票の記入してきてもらうことと、千田が作成した認知の特徴のシートのチェックを行うこととした。
※認知モデル/認知行動モデルとは、認知行動療法で状態を説明するときに用いる方法。
簡単に言うと、状況に対してどのような認知(捉え方)をしたかによって、気分や行動、身体化に影響を及ぼすという仮説である。
状況⇒認知(物事の捉え方)⇒気分-行動-身体化
2セッション(1週間後)
前回の施術後の確認。鍼当たりがあったかどうかなどネガティブな要因と考え方などのポジティブな変化についての確認を行う。
以後、2セッション~14セッション(8セッション以降は頻度は隔週、12セッション~は1か月に1回とした)の終了まで鍼施術内容に変化はない。
ホームワークは、認知再構成法という技法を用いるために、3つのコラムという方法の説明を行い自宅で行ってもらう。
3つのコラムとは、状況-気分-自動思考に分けて書き込んでいくことである。
自動思考とは、その一瞬に頭に浮かんだことや考え、イメージ。
3セッション~4セッション
3つのコラムはうまく書けていたために、その中の一つを用いてネガティブな考え方の修正を加える一つの方法を指導する。
ホームワークは、3つのコラムの継続
5セッション~7セッション
6セッション時には、鍼を行うと頭の中がスッキリする感じがするといい始める。
前の2セッションで行ったネガティブな考え方の修正をアドバイスなしにできるかを練習する。
ホームワークは、5つのコラムといって、状況-気分-自動思考-根拠-反証に分けて書き込む方法を行ってもらう。
また、6セッション以降はホームワークにウォーキング(早歩き)を日に20分を追加した。
8セッション以降
9セッション時には、ネガティブな考えが出るがすぐに別な考えも浮かべられるようになってきている。と言い始める。
12セッション終了後に職場復帰となる。
ホームワークは、7つのコラムといって、状況-気分-自動思考-根拠-反証-適応的思考-気分に分けて書き込む方法を行ってもらう。
なお、11セッションと12セッションは、職場復帰が決まったために復帰への不安感が強くなったために、この2セッションは、施術時間を90分として認知行動療法の時間を60分取り復帰へのネガティブな考えの修正を行った。
14セッション
症状もなく職場でも問題なくできているということで、3か月後に再度状態を確認(フォローアップ)するために来ていただきたいことをお願いして終了となる。
3か月後も問題なしであった。
2、脳血流改善を目的に、頭のてっぺん付近(ツボ名は百会)と眉間(ツボ名は印堂)に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分程度)
3、脳血流改善を目的に、特に左前頭葉の2か所に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分程度)
4、耳に置鍼(20分程度)(脳血流が改善することがわかっている)
5、患者さんが希望したときのみ、背部と頸部にに置鍼(20分程度)
※置鍼とは、鍼を刺入した状態で置いておくこと。
初診時
現在の困りごとを伺いうつ病のテストとしてQIDS -Jを行う。
次に、症状や状態の説明を認知モデル/認知行動モデルで説明を行った後に、認知行動療法を行いその後、上記の内容の鍼施術を行った。
ホームワークとしては、CMI健康調査票の記入してきてもらうことと、千田が作成した認知の特徴のシートのチェックを行うこととした。
※認知モデル/認知行動モデルとは、認知行動療法で状態を説明するときに用いる方法。
簡単に言うと、状況に対してどのような認知(捉え方)をしたかによって、気分や行動、身体化に影響を及ぼすという仮説である。
状況⇒認知(物事の捉え方)⇒気分-行動-身体化
2セッション(1週間後)
前回の施術後の確認。鍼当たりがあったかどうかなどネガティブな要因と考え方などのポジティブな変化についての確認を行う。
以後、2セッション~14セッション(8セッション以降は頻度は隔週、12セッション~は1か月に1回とした)の終了まで鍼施術内容に変化はない。
ホームワークは、認知再構成法という技法を用いるために、3つのコラムという方法の説明を行い自宅で行ってもらう。
3つのコラムとは、状況-気分-自動思考に分けて書き込んでいくことである。
自動思考とは、その一瞬に頭に浮かんだことや考え、イメージ。
3セッション~4セッション
3つのコラムはうまく書けていたために、その中の一つを用いてネガティブな考え方の修正を加える一つの方法を指導する。
ホームワークは、3つのコラムの継続
5セッション~7セッション
6セッション時には、鍼を行うと頭の中がスッキリする感じがするといい始める。
前の2セッションで行ったネガティブな考え方の修正をアドバイスなしにできるかを練習する。
ホームワークは、5つのコラムといって、状況-気分-自動思考-根拠-反証に分けて書き込む方法を行ってもらう。
また、6セッション以降はホームワークにウォーキング(早歩き)を日に20分を追加した。
8セッション以降
9セッション時には、ネガティブな考えが出るがすぐに別な考えも浮かべられるようになってきている。と言い始める。
12セッション終了後に職場復帰となる。
ホームワークは、7つのコラムといって、状況-気分-自動思考-根拠-反証-適応的思考-気分に分けて書き込む方法を行ってもらう。
なお、11セッションと12セッションは、職場復帰が決まったために復帰への不安感が強くなったために、この2セッションは、施術時間を90分として認知行動療法の時間を60分取り復帰へのネガティブな考えの修正を行った。
14セッション
症状もなく職場でも問題なくできているということで、3か月後に再度状態を確認(フォローアップ)するために来ていただきたいことをお願いして終了となる。
3か月後も問題なしであった。
 施術回数・頻度・期間
施術回数・頻度・期間
施術回数:14回
頻度:週1回~隔週1回で治療終盤は月に1回
期間:6カ月プラス3か月後の確認セッション
頻度:週1回~隔週1回で治療終盤は月に1回
期間:6カ月プラス3か月後の確認セッション
 施術後のケア
施術後のケア
1、草野球チームの練習とゴルフの練習は仕事の忙しさにかかわらず、生活スケジュールの中に組み込むようにしてもらう。
2、ネガティブな感情が出てきたり、しんどくなりそうだなと思ったらすぐに来ることを伝える。(すぐの段階で来ていただければ1回とか2回の鍼治療で終わる場合が多いからです)
2、ネガティブな感情が出てきたり、しんどくなりそうだなと思ったらすぐに来ることを伝える。(すぐの段階で来ていただければ1回とか2回の鍼治療で終わる場合が多いからです)