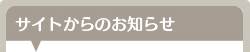リスタ・コンディショニング・ルームの施術例

薬を自己判断でやめたことによる離脱症状で苦しまれていたうつ病の方
-
全身
-
婦人科
-
メンタル
-
女性
-
30代
2022.12.29
 病院での診断
病院での診断
うつ病
 これまでの経過
これまでの経過
※今回の掲載は本人に了解を得ている事例であることと、個人を特定できないように施しております。
職場での人間関係問題と仕事に対する能力不足を感じながら仕事を行っていた結果、2年前にうつ病となる。
精神科でお薬を処方されて飲んでいた。
少しずつではあるがよくなってきて、薬も多少ではあるが飲む量も減ってはきていた。
ただ、2年間も薬を飲まないといけないとは思っていなかった。また、以前より夫婦ともに子供が欲しいと思っており、自分の年齢的なものを考えて薬を自己判断でやめてしまう。
そのことで、以下の離脱症状があらわれる。
離脱症状「頭痛・だるさ・しびれ・耳鳴り(シャンシャン鳴る)」と「イライラ・不安・不眠・ソワソワ感」
薬は飲みたくなかったので、何か治療法はないかとネットで検索していた時に当ルームのホームページの「心療鍼灸」という項目を見つけ来室。
職業:会社員(事務系)
性格:真面目、思い込みが激しい、外交的、考え方で人とぶつかることが度々
既往歴(過去に大きな病気をした経験):特になし
お酒:ほとんど飲まない
タバコ:吸わない
趣味:ゲーム
家族:夫・30代
結婚:4年・夫婦仲は良好
夫婦ともに子供を希望している。
職場での人間関係問題と仕事に対する能力不足を感じながら仕事を行っていた結果、2年前にうつ病となる。
精神科でお薬を処方されて飲んでいた。
少しずつではあるがよくなってきて、薬も多少ではあるが飲む量も減ってはきていた。
ただ、2年間も薬を飲まないといけないとは思っていなかった。また、以前より夫婦ともに子供が欲しいと思っており、自分の年齢的なものを考えて薬を自己判断でやめてしまう。
そのことで、以下の離脱症状があらわれる。
離脱症状「頭痛・だるさ・しびれ・耳鳴り(シャンシャン鳴る)」と「イライラ・不安・不眠・ソワソワ感」
薬は飲みたくなかったので、何か治療法はないかとネットで検索していた時に当ルームのホームページの「心療鍼灸」という項目を見つけ来室。
職業:会社員(事務系)
性格:真面目、思い込みが激しい、外交的、考え方で人とぶつかることが度々
既往歴(過去に大きな病気をした経験):特になし
お酒:ほとんど飲まない
タバコ:吸わない
趣味:ゲーム
家族:夫・30代
結婚:4年・夫婦仲は良好
夫婦ともに子供を希望している。
 鍼灸院としての診断
鍼灸院としての診断
精神科でうつ病と診断されているので、QIDS -JとCMI健康調査票を用いて現在の状態の確認をした。
QIDS -J(簡易抑うつ症状尺度):15(中等度)
CMI健康調査票:領域Ⅳ(神経症の可能性が高い)
なお、身体的自覚症の項目では、目と耳/神経系/疲労度/習慣が高得点であるのと、精神的自覚症の項目では、不適応/抑うつ/不安/緊張が高得点であった。
※CMI健康調査票は身体的自覚症(12系統別)と精神的自覚症(6状態別)を把握と、そこから神経症(ストレスによって精神が疲弊した状態)かどうかの確認をする検査
QIDS -J(簡易抑うつ症状尺度):15(中等度)
CMI健康調査票:領域Ⅳ(神経症の可能性が高い)
なお、身体的自覚症の項目では、目と耳/神経系/疲労度/習慣が高得点であるのと、精神的自覚症の項目では、不適応/抑うつ/不安/緊張が高得点であった。
※CMI健康調査票は身体的自覚症(12系統別)と精神的自覚症(6状態別)を把握と、そこから神経症(ストレスによって精神が疲弊した状態)かどうかの確認をする検査
 治療方針
治療方針
当初は鍼治療のみを行い、途中より認知行動療法を併用して進める。
施術をはじめるにあたって、患者さんに以下の2つの項目について約束をしてもらった。
1、自殺について、施術が始まって当ルームに通われている間は絶対に行わない。
2、2週間(4回)から3週間(6回)鍼治療を行っても改善が見られない場合は、再度お薬を飲んでいただく。
※1、の自殺については、自殺企図があったり精神症状が強い病気の場合はすべての患者さんに約束をしていただく。
精神科や精神疾患を対象に行っている心理師は、日常的に行っているので今回も行った。
鍼治療として、
症状が強いために当初3週間は週2回のペースで行い症状の回復具合等の様子を見たのち、その後は週1回のペースで行うこととする。
1、うつ病の場合、脳の血流量が低下しているために脳血流の改善とセロトニンの活性化。
2、特に左前頭葉の血流量の改善。(うつ病は左前頭葉の血流量が低下していることが研究などで報告されている)
3、上記の1、の目的同様に耳鍼と眼窩上神経、眼窩下神経、オトガイ神経に置鍼。
4、頭部や背部、頸部の症状に対しては、訴えたときのみ対応する。
5、ホームワーク(自宅で行ってもらうこと):ウォーキングなどの運動療法や認知行動療法の技法、行動活性化という方法を用いる。
今回は、うつ気分をはじめネガティブな気分と身体症状が主な訴えのため、当初は鍼治療のみを行い、途中から認知行動療法の併用とホームワーク(自宅で行ってもらうこと)で施術を進めることとした。
方法としては、施術時間は50分で当初は鍼治療のみ、途中からは、はじめに認知行動療法を20分~30分、その後鍼治療を20分~30分で行うこととした。
施術をはじめるにあたって、患者さんに以下の2つの項目について約束をしてもらった。
1、自殺について、施術が始まって当ルームに通われている間は絶対に行わない。
2、2週間(4回)から3週間(6回)鍼治療を行っても改善が見られない場合は、再度お薬を飲んでいただく。
※1、の自殺については、自殺企図があったり精神症状が強い病気の場合はすべての患者さんに約束をしていただく。
精神科や精神疾患を対象に行っている心理師は、日常的に行っているので今回も行った。
鍼治療として、
症状が強いために当初3週間は週2回のペースで行い症状の回復具合等の様子を見たのち、その後は週1回のペースで行うこととする。
1、うつ病の場合、脳の血流量が低下しているために脳血流の改善とセロトニンの活性化。
2、特に左前頭葉の血流量の改善。(うつ病は左前頭葉の血流量が低下していることが研究などで報告されている)
3、上記の1、の目的同様に耳鍼と眼窩上神経、眼窩下神経、オトガイ神経に置鍼。
4、頭部や背部、頸部の症状に対しては、訴えたときのみ対応する。
5、ホームワーク(自宅で行ってもらうこと):ウォーキングなどの運動療法や認知行動療法の技法、行動活性化という方法を用いる。
今回は、うつ気分をはじめネガティブな気分と身体症状が主な訴えのため、当初は鍼治療のみを行い、途中から認知行動療法の併用とホームワーク(自宅で行ってもらうこと)で施術を進めることとした。
方法としては、施術時間は50分で当初は鍼治療のみ、途中からは、はじめに認知行動療法を20分~30分、その後鍼治療を20分~30分で行うこととした。
 治療内容
治療内容
1、脳血流改善を目的に、四肢末端への鍼治療プラス低周波鍼通電(20分~30分程度)(どこのツボではなく肘から先と膝から先に鍼治療を行うことで、脳血流が改善することがわかっている)
2、脳血流改善を目的に、頭のてっぺん付近(ツボ名は百会)と眉間(ツボ名は印堂)に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分~30分程度)
3、脳血流改善を目的に、特に左前頭葉の2か所に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分~30分程度)
4、耳と眼窩上神経(ツボ名は陽白)、眼窩下神経(ツボ名は四白)、オトガイ神経(ツボ名は大迎)に置鍼(20分~30分程度)(脳血流が改善することがわかっている)
5、患者さんが希望したときのみ、背部と頸部、頭部に置鍼(20分程度)
※置鍼とは、鍼を刺入した状態で置いておくこと。
初診時
現在の困りごとを伺いうつ病のテストとしてQIDS -Jを行う。
次に、症状や状態の説明を認知モデル/認知行動モデルで説明を行った後に鍼施術を行った。
ホームワークとしては、CMI健康調査票の記入してきてもらうことと、千田が作成した認知の特徴のシートのチェックを行うこととした。
※認知モデル/認知行動モデルとは、認知行動療法で状態を説明するときに用いる方法。
簡単に言うと、状況に対してどのような認知(捉え方)をしたかによって、気分や行動、身体化に影響を及ぼすという仮説である。
状況⇒認知(物事の捉え方)⇒気分-行動-身体化
2セッション(3日後)
前回の施術後の確認。鍼当たりがあったかどうかなどネガティブな要因と考え方などのポジティブな変化についての確認を行う。
以後、2セッション~6セッション(週に2回とした)
患者さんが訴えていた離脱症状「頭痛・だるさ・しびれ・耳鳴り(シャンシャン鳴る)」と「イライラ・不安・不眠・ソワソワ感」の軽減が確認できたために、継続して施術をすることとした。
7セッション以降は頻度は週に1回ペースとした。
11セッション~は認知行動療法を併用した。
19セッション~は隔週とした。
7セッション~10セッション
2セッション時と鍼治療内容に変更はない。
10セッション時には、離脱症状「しびれ・耳鳴り(シャンシャン鳴る)」と「不安・ソワソワ感」の4症状のみが残っている。
ホームワークとして、8セッションからはウォーキング(普段より早めのペースで歩いてもらう)を行うこととした。
11セッション~18セッション
鍼治療の施術部位に変更はないが時間を20分間として、認知行動療法の併用を行うようにした。
15セッション時には、気にならない程度ではあるが耳鳴り(シャンシャン鳴る)が残っている状態であった。
ホームワークは、認知再構成法という技法を中心にいくつかの認知技法と行動技法を用いることにした。
18セッション~22セッション
鍼治療の施術部位と認知行動療法の併用を行うことに変更はないが、施術間隔を隔週から1か月1回とした。
22セッション時
症状もなく妊活をスタートしたということで、3か月後に再度状態を確認(フォローアップ)するために来ていただきたいことをお願いして終了となる。
3か月後も問題なしであった。
2、脳血流改善を目的に、頭のてっぺん付近(ツボ名は百会)と眉間(ツボ名は印堂)に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分~30分程度)
3、脳血流改善を目的に、特に左前頭葉の2か所に鍼治療プラス低周波鍼通電(20分~30分程度)
4、耳と眼窩上神経(ツボ名は陽白)、眼窩下神経(ツボ名は四白)、オトガイ神経(ツボ名は大迎)に置鍼(20分~30分程度)(脳血流が改善することがわかっている)
5、患者さんが希望したときのみ、背部と頸部、頭部に置鍼(20分程度)
※置鍼とは、鍼を刺入した状態で置いておくこと。
初診時
現在の困りごとを伺いうつ病のテストとしてQIDS -Jを行う。
次に、症状や状態の説明を認知モデル/認知行動モデルで説明を行った後に鍼施術を行った。
ホームワークとしては、CMI健康調査票の記入してきてもらうことと、千田が作成した認知の特徴のシートのチェックを行うこととした。
※認知モデル/認知行動モデルとは、認知行動療法で状態を説明するときに用いる方法。
簡単に言うと、状況に対してどのような認知(捉え方)をしたかによって、気分や行動、身体化に影響を及ぼすという仮説である。
状況⇒認知(物事の捉え方)⇒気分-行動-身体化
2セッション(3日後)
前回の施術後の確認。鍼当たりがあったかどうかなどネガティブな要因と考え方などのポジティブな変化についての確認を行う。
以後、2セッション~6セッション(週に2回とした)
患者さんが訴えていた離脱症状「頭痛・だるさ・しびれ・耳鳴り(シャンシャン鳴る)」と「イライラ・不安・不眠・ソワソワ感」の軽減が確認できたために、継続して施術をすることとした。
7セッション以降は頻度は週に1回ペースとした。
11セッション~は認知行動療法を併用した。
19セッション~は隔週とした。
7セッション~10セッション
2セッション時と鍼治療内容に変更はない。
10セッション時には、離脱症状「しびれ・耳鳴り(シャンシャン鳴る)」と「不安・ソワソワ感」の4症状のみが残っている。
ホームワークとして、8セッションからはウォーキング(普段より早めのペースで歩いてもらう)を行うこととした。
11セッション~18セッション
鍼治療の施術部位に変更はないが時間を20分間として、認知行動療法の併用を行うようにした。
15セッション時には、気にならない程度ではあるが耳鳴り(シャンシャン鳴る)が残っている状態であった。
ホームワークは、認知再構成法という技法を中心にいくつかの認知技法と行動技法を用いることにした。
18セッション~22セッション
鍼治療の施術部位と認知行動療法の併用を行うことに変更はないが、施術間隔を隔週から1か月1回とした。
22セッション時
症状もなく妊活をスタートしたということで、3か月後に再度状態を確認(フォローアップ)するために来ていただきたいことをお願いして終了となる。
3か月後も問題なしであった。
 施術回数・頻度・期間
施術回数・頻度・期間
施術回数:22回
頻度:週1回~隔週1回で治療終盤は月に1回
期間:7カ月プラス3か月後の確認セッション
頻度:週1回~隔週1回で治療終盤は月に1回
期間:7カ月プラス3か月後の確認セッション
 施術後のケア
施術後のケア
1、生活習慣にヨガなどの興味のある運動を取り入れていただくこと。
2、ネガティブな感情が出てきたり、しんどくなりそうだなと思ったらすぐに来ることを伝える。(すぐの段階で来ていただければ1回とか2回の鍼治療で終わる場合が多いからです)
2、ネガティブな感情が出てきたり、しんどくなりそうだなと思ったらすぐに来ることを伝える。(すぐの段階で来ていただければ1回とか2回の鍼治療で終わる場合が多いからです)