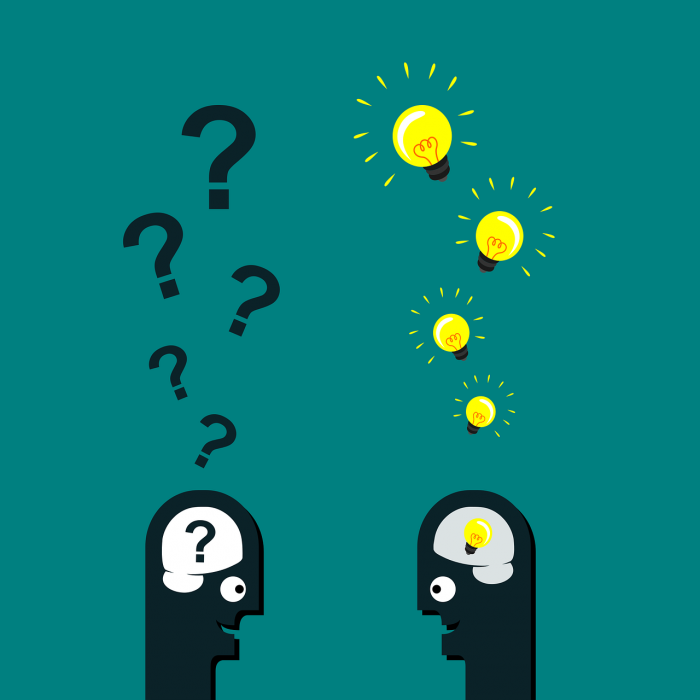しかし、ただ質問を投げかけるだけでは、患者さんの本当の悩みや根本的な問題を引き出すことはできません。
ここで重要になるのが、「質問の仕方」です。
本記事では、コーチングにおける「質問」の考え方を活かし、鍼灸院の問診をより効果的にする方法を解説します。
以下5つのポイントのなかで、やっていないものがどれかを抽出したうえで実践してみてください
1.「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」を使い分ける
・オープンクエスチョン(開かれた質問)
患者さんの自由な答えを引き出し、より多くの情報を得るために使います。
例:「肩の痛みはどのような時に特に強くなりますか?」(具体的な答えを引き出せる)
・クローズドクエスチョン(閉じた質問)
「はい・いいえ」で答えられる質問で、特定の情報を確認するのに適しています。
例:「朝と夜、どちらのほうが痛みが強いですか?」(選択肢を与える)
オープンクエスチョンで得た情報を補足・確認する形でクローズドクエスチョンを使うと、より具体的な診断につながります。
2. 「患者さんの気づきを促す質問」を意識する
患者さんが自分の身体の状態を深く理解できるような質問を投げかけることが重要です。
例:
「肩の痛みを感じたのはいつからですか?」
「その痛みが始まる前に、何か生活習慣の変化はありましたか?」
こうした質問をすることで、患者さん自身が「痛みの原因」に気づくことができ、治療に対する納得感が高まります。
3. 「肯定的な質問」で患者さんのモチベーションを高める
治療の効果を実感しやすくするために、ポジティブな視点を引き出す質問が有効です。
例:
「痛みがなくなったことってありますか?」(痛みにフォーカス)
「これまでに少しでも楽になったことはありましたか?」(改善にフォーカス)
ポジティブな質問をすることで、患者さんの「治療を受ける意味」が明確になり、積極的に通院しようという意欲につながります。
4. 「沈黙を恐れず、待つ」
患者さんがすぐに答えられなくても焦らず待つことが重要です。
例:
(患者さんが考える時間を待ち、必要なら「どうぞ、ゆっくり考えてください」と伝える)
患者さんが沈黙したときは「自分の体と向き合う時間」になっている可能性があるので、無理に会話を埋めようとしないことがポイントです。
5. 「患者さん主体の問診」を意識する
患者さんの話をしっかり聞き、「治療を受けるのは患者さん自身である」ことを意識した質問をすることが大切です。
例:
「この治療をやっておきますね。」(施術者主体)
患者さんが自分で「こうなりたい」と思えることで、治療の効果を実感しやすくなります。
「質問の仕方」を工夫することで、患者さんの本音や根本的な問題を引き出しやすくなります。
また、患者さん自身が「なぜ治療が必要なのか」を理解することで、治療の継続率や満足度も向上します。
鍼灸院の問診を、単なる情報収集の場ではなく、「患者さんが自分の体と向き合い、前向きに治療に取り組むきっかけ」にできるよう、ぜひコーチングの「質問」の視点を活用してみてください。
本記事では、コーチングにおける「質問」の考え方を活かし、鍼灸院の問診をより効果的にする方法を解説します。
以下5つのポイントのなかで、やっていないものがどれかを抽出したうえで実践してみてください
1.「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」を使い分ける
・オープンクエスチョン(開かれた質問)
患者さんの自由な答えを引き出し、より多くの情報を得るために使います。
例:「肩の痛みはどのような時に特に強くなりますか?」(具体的な答えを引き出せる)
・クローズドクエスチョン(閉じた質問)
「はい・いいえ」で答えられる質問で、特定の情報を確認するのに適しています。
例:「朝と夜、どちらのほうが痛みが強いですか?」(選択肢を与える)
オープンクエスチョンで得た情報を補足・確認する形でクローズドクエスチョンを使うと、より具体的な診断につながります。
2. 「患者さんの気づきを促す質問」を意識する
患者さんが自分の身体の状態を深く理解できるような質問を投げかけることが重要です。
例:
「肩の痛みを感じたのはいつからですか?」
「その痛みが始まる前に、何か生活習慣の変化はありましたか?」
こうした質問をすることで、患者さん自身が「痛みの原因」に気づくことができ、治療に対する納得感が高まります。
3. 「肯定的な質問」で患者さんのモチベーションを高める
治療の効果を実感しやすくするために、ポジティブな視点を引き出す質問が有効です。
例:
「痛みがなくなったことってありますか?」(痛みにフォーカス)
「これまでに少しでも楽になったことはありましたか?」(改善にフォーカス)
ポジティブな質問をすることで、患者さんの「治療を受ける意味」が明確になり、積極的に通院しようという意欲につながります。
4. 「沈黙を恐れず、待つ」
患者さんがすぐに答えられなくても焦らず待つことが重要です。
例:
(患者さんが考える時間を待ち、必要なら「どうぞ、ゆっくり考えてください」と伝える)
患者さんが沈黙したときは「自分の体と向き合う時間」になっている可能性があるので、無理に会話を埋めようとしないことがポイントです。
5. 「患者さん主体の問診」を意識する
患者さんの話をしっかり聞き、「治療を受けるのは患者さん自身である」ことを意識した質問をすることが大切です。
例:
「この治療をやっておきますね。」(施術者主体)
患者さんが自分で「こうなりたい」と思えることで、治療の効果を実感しやすくなります。
「質問の仕方」を工夫することで、患者さんの本音や根本的な問題を引き出しやすくなります。
また、患者さん自身が「なぜ治療が必要なのか」を理解することで、治療の継続率や満足度も向上します。
鍼灸院の問診を、単なる情報収集の場ではなく、「患者さんが自分の体と向き合い、前向きに治療に取り組むきっかけ」にできるよう、ぜひコーチングの「質問」の視点を活用してみてください。